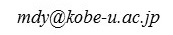山中大学ホームページ
山中大学ホームページ
工事中!!!! 工事中!!!!
「地球科学」は, この巨大な有機体の体調を診断することによって, そのメカニズムを解明する生理学であるとともに, 罹病を予防する医学であると言える. 人体の医学に多くの科が細分化されて存在するように, 地球本体(地震・火山)・水圏(海洋・陸水・雪氷)・ 大気圏(気象・超高層物理)などの多くの分野が, それぞれの固有の歴史的背景と学問的基盤に基づいて専門化されてきた. しかし現在の我々が直面するものは, 地球という有機体の全体に関わる病気であり, これを根本的に治癒しようとする大手術である.
1980年代後半から, 環境という語は国際政治のスローガンとなり, 国内的にもあまたの大学の新コースの名称となった. 文部省「新プログラム」をはじめとする比較的大型の新しい予算措置が講ぜられ, 「環境バブル」と揶揄されるほどであったが, これらの施策によってようやく地球という有機体の診察方法, つまり地球環境を科学的に論じることのできる 手段(観測の技術や方法論)の基礎が確立されたに過ぎないのである. 来る21世紀に本格化すると予想される大手術を前に, 本稿では一人の地球医療技術者としての決意を語りたい.
重要なことは, 上記のような状況をもってしても, 地球環境全体の現状の診断にもまだまだ不十分であり, また45億年の地球の歴史を考えるとき, それらの全てを恒久的に維持していくことが必須となることである. 人体の場合には人間ドックは一晩で済むが, 地球の場合はそうはいかないのである. したがって地球環境の観測的研究の規模は, 今後ますます大きくなると考えられ, またそうしないと人類は地球環境の正しい把握・予測をすることができない. これが, 何号か前の対談において住教授が言われた, 地球科学の「巨大科学」化の一つの側面である. しかし巨大とは単に予算や装置や人員の規模だけではない. 全ての学問, 全ての英知を結集するという意味での巨大さである. この全てとは人類全てであって, 学際化のみならず国際化をも必然的に意味する.
我が国にとっての国際化とは, 明治以来ともすれば欧米に追い付き模倣することであった. 科学において模倣は決して悪いことではなく, 研究とは基本的に先輩の模倣から始まるものである. しかし我が国の地球科学は既に世界の先端にあり, かつ人類が今直面するのはかつて誰も経験しなかったような大手術である. 我が国の研究者とそれを支える科学政策に, かつてない大きな覚悟と転換が必要であることは自明である. 特に, 本誌でも既に何回か特集が組まれているアジア地域との共同研究の問題は, 単に予算の問題ではなく, 脱亜入欧的な蔑視と過去の犯罪的戦争のしこりが生んだ様々の制度上の制約, また研究者の側においても研究対象としてしか相手国を見ない思慮の浅さ, などがあって決して容易ではない. 大切なことは, 地球環境とは, 日本の大学の我々が興味があるから(あるいはそれをやるだけの 設備と能力があるから)研究するものではなくて, あらゆる国の全ての人々が共に必要なものであるからこそ 研究すべきものなのである.
名医は必ずしも大医学者ではない. これは, 適切な正しい診断を下すには, 患者の側に立った注意深い診察と治療こそが重要なのであって, 大学の講義や専門書などで習うような知識や理屈ではない, という意味で言い古された言葉ではある. しかし地球環境という患者を前にした場合は, 医者自身も実は患者の体の一部に過ぎないために, もう一つの意味がある. 適切な診断とは, 医学的に正しいかどうかではなく, 他のどの医者が見ても同じ診断が下せるものであるかどうかである. 注意すべきは, ここでは(医学も実は同じかもしれないが)地球科学には完全な正解はない ということではなくて, どの国の研究者が見てもなるほどと理解できるような処方箋を示せないと 地球環境に関する科学的アセスメントをしたことにはならない, ということを言いたいのである.
科学技術の発展は, かつては全て人類にとって良いことづくめであったが, 最近はどちらかと言えば逆の印象が持たれている. これを跳ね返すために, さらに新しくさらに良い技術(CMに出て来る環境に優しいというのもあろうし, 環境をより精密に測れるというのもあってよい)を作ろうとしている 科学者・研究者が, 我が国にも大勢おられる. しかし別の方向として, 現在ともすれば人間性から最も遠いと誤解されがちな自然科学が そもそもは人間の思索の産物であること, %%%SF映画のようにコンピュータが計算した算数の結果ではないということを. また西洋起源の今の自然科学体系の限界が近年少なからず叫ばれていることにも 注目したい. つまり, もともと東洋には自然・生物・人間を一体と見る, 現在の自然科学とはかなり異質の考え方があり, そういう意味で現在の地球環境問題のカベや地球科学のさらなる発展の糸口は, 東洋つまりアジア地域に住む我々こそが協力して観測を行い, 我々が遠い祖先から受け継いで来た自然観に立脚して深く考えれば 見つけられるかもしれない, ということである.
しかるに近年に至って, 例えば大気が逆に海面をコントロールする面をも対等に重視した, 大気・海洋「相互作用」というパラダイムが, 次第に従来の通念を駆逐しつつある. この新しいパラダイムによって, 良く知られた数年スケールの全地球的気候変動である 「エルニーニョ南方振動」(ENSO)現象が, 全地球大気・海洋が一体となって自励的に変動している現れとして 理解されるようになった. 前節で触れたWCRPでは, 1990年前後に副計画「熱帯海洋全球大気大循環研究計画」(TOGA)を実施し, 現在も副計画「世界海洋循環研究計画」(WOCE)の中で 大気・海洋相互作用メカニズムの観測・研究を推進している. このような地球環境自身が, まさに自然に引き起こしている内部変動は, 先述の様々の外的作用を緩和して現在の状況を長期的に維持する ホメオスタシスであると考えられており, 地球環境という有機体の維持を考える上で極めて重要なパラダイムである.
同様な意味で, 地表・海表から大気への水蒸気の蒸発と, 大気から地表・海表へ降り注ぐ雨とを仲立ちとする, 大気・陸面相互作用もまた主要な研究課題となりつつある. これはやはりWCRP副計画「全球エネルギー水循環研究計画」(GEWEX)の下で, 日本(筑波大の安成教授ら)が世界に向けて提唱した初めての大規模国際計画 である「GEWEXアジアモンスーン研究計画」(GAME)として, 本年から本格的に開始された. モンスーンは, 季節に依存した現象ではあるが, 単に球面をもつ地球の緯度によるのではなく, むしろ海陸分布や海陸の表面状態など, 経度方向に顕著に依存した現象であり, 熱帯とか温帯というような概念とは一線を画するものである. 経度方向に依存した, つまり東西方向の大気循環は, ENSOなど数年以上のスケールにも極めて重要であることがわかってきており, 観測点の数を一層増す必要がここでも生じて来る.
また陸面や海洋中に存在する生物圏は, 本稿冒頭に述べたように我が地球大気を規定する上で欠かせないものであったが, 現在は人間活動に伴う近年の急激な生物圏の変質を主要な動機として, 地球の歴史に比べて極めて短い時間スケールで生じる様々の 大気・海洋と生物圏との間の相互作用が重視されてきている. これはWCRPとは別個の大型プロジェクト「国際地球圏生物圏研究計画」(IGBP)と して策定され, 熱帯林焼失(バイオマスバーニング)が大気組成に与える影響などに関する 「大気化学研究計画」(IGAC)などが推進されつつある.
大気圏の内部においても, かつては下層(高密度)の対流圏が 上層(低密度)の成層圏やさらにその上の中間圏・超高層大気を一方的 に規定しているものとされ, 社会的に大きく注目された南極春季成層圏の「オゾンホール」現象も, そのような下方からのオゾン破壊物質の強制的流入のみで捉えられていた. しかし現在では, 赤道域成層圏に見られる約2年周期の東西風交替(準2年周期振動; QBO)や, 冬季極域成層圏に突発的に現れる異常高温(成層圏突然昇温; SSW)などとも 密接に関連した, 全地球的な対流圏・成層圏の相互作用の一側面として理解されている. これは1990年代前半には国際プロジェクト「太陽地球系エネルギー研究計画」 (STEP)の主要課題として, 太陽変動やこれに直接誘発された超高層大気変動との関連とともに 観測・研究が推進された後, 現在はWCRPの副計画「成層圏起源気候変動研究計画」(SPARC)としての 立案が進められている.
なお今述べたSTEPと, 先に触れたWCRP-TOGA, さらに生態学的な観測・研究の一部までが, 我が国では1990年代前半に一つの文部省新プログラム 「アジア太平洋域を中心とした地球環境変動の研究」 として一括して進められたことは特筆に値する. 現在はこの3つの流れは一応別個の計画(例えばGEWEX-GAME, SPARC) に沿って進められているが, 本稿で強調している一つの有機体としての地球環境という見方を 具体的に形にしようとした点で, 新プログラムの意義は, 個々の研究成果に増して大きいものである. さらにこのような先見的行動は, 諸外国においては殆どなされず, 我が国の研究者グループのみが着手したことも必ず後世に記憶されるであろう.
新プログラムの一環として新たに設立された東京大学気候システム研究センター, 京都大学生態学研究センターなどでは, 若手研究者によって今述べたような新しい側面の地球環境科学の萌芽が すくすくと育ちつつある. また新プログラムの成功は, 名古屋大学の太陽地球環境研究所と大気水圏科学研究所, 東京大学海洋研究所, 北海道大学低温科学研究所, 京都大学防災研究所というような既存組織の拡充や発展的改組にも, 間接的に大きく貢献した. 手前味噌であるが, 筆者の所属する京都大学超高層電波研究センターも, 新プログラムにおけるSTEP的側面の中核として貢献し, それ以前の成層圏〜超高層大気の結合からさらに進んで, 対流圏・水圏まで視野を広げるとともに, 後述の赤道域の総合科学という新しい構想を大きく前進させることができたと 自負している. これらの研究所・センターは全体として, 地球環境の総合的診断つまり人間ドック機能を有する総合病院のような 役割を果たすことが期待されている.
大気・海洋の波動は, 大循環や対流などの直接作用と本質的に異なる「遠隔作用」であり, よく知られた電磁波放射過程と同様にエネルギーや運動量のバランス状態, つまり「場」の構成要素である. 我々が簡単に見られる海面と同様に, 対流圏と成層圏の境界である「対流圏界面」も波立っており, %%両圏間のエネルギー・運動量・物質の「輸送」を支配している また海洋や大気の内部にも波が存在している. すなわち海洋や対流圏や成層圏という各領域は, 波動という遠隔作用によってそれぞれの構造を基本的には保持したまま 相互に関係し合い, かつ両者に加えて波動という目に見えない領域を含めて全体として バランスしているのである. なお波動が循環・対流を生成したり, 逆に直接作用から波動が生成されることももちろん大いにあり得る. %%海面と同様に波立つ対流圏・成層圏の混合領域として、 %%まさに波動という見えない場が不断に顕在化している場所という %%認識への転換である。 形の決まった一つの波は限られた領域・時間にしか存在しないので, そのような個々の波の素過程を捉え論じるのよりむしろ, ランダムな波動の集合としての全体的振舞を把握し記述することが, 特に地球環境とその変動を考える上では重要となる.
先に触れた大型レーダー, および大型衛星搭載の各種大気運動測定器は, 上記のような認識のもとに開発・使用されている. 後者は前者では把握できない全球的な観測を行えるが, かつ消えかつ結ぶ小規模な波の観測は後者では無理で前者でのみ可能である. そこで最近, 全世界に既に展開している気象観測網の古典的測器(気球観測)を, 大型レーダーで標準化した上で用いて, 小規模な波の全球的分布を把握しようとする試みが始まっている. 対流圏の小規模変動は, 雲や雨域として古典的な気象衛星や気象レーダーでも観測できるが, 風速変化を直接得るためには, やはり相互比較した上で少数の大型レーダーを用いることなどが必要である. このように, それぞれ固有の長所・短所をもつ各種測器を同時に用いて, 各データを「相補的」に解析していることが, 現在の大気・海洋観測の大きな特徴である.
もう一つの根幹である微物理化学は, 雲や雨の生成や局所的大気汚染の関係では決して新しいものではない. しかし主として閉鎖系での室内実験や原子・分子の理論に基いて得られた知見が, 地球大気・海洋という完全な開放系で巨視的(流体)運動を内在し, さらに生物圏というそれ自身複雑な外的要素を伴って存在するとき, 果たして定量的にそのまま拡張できるかは自明ではない. 最近発展してきた地上・衛星搭載の両方の光学的測器, 大気観測専用に設計された気球・航空機つまり空飛ぶ実験室を用いた直接測定などは, それらの未解決の問題を打開することが期待されている. 大気・海洋間の物質交換の研究や, 雲や雨を作る過程まで考慮した地球・大気・宇宙空間の熱収支の問題など も最近本格化したばかりであり, 炭酸ガスの増大が必ずしも地球温暖化に結びつくとはまだ言い切れない. また微物理的には同じ条件(になり得る)にも拘らず, 例えば集中豪雨などのように結果に極めて不均一が生じることなどの解決には, 微物理と力学の結合(例えば波動によって組織化された雲の発達の研究)が必須である.
以上に述べたような新しい学問的枠組や観測的知見を次々と取り入れて, まさに微小スケールから地球規模まで再現できるような数値モデルの構築も, 今や夢ではなくなってきた. 数値モデルを利用して観測しきれない場所・時刻・種類の物理量を埋める 「4次元同化」や「リトリーバル」の手法も提案されてきている. ただ巨大な数値モデルの結果は, それ自身一つの(バーチャルリアリティとしての)自然に他ならず, 結局は現実の地球環境を観測するのと(複雑さにおいて) 同じ困難さがつきまとう. そういう意味で, 地球環境観測の進展状況は, 医療技術のそれとよく似ている. つまり根本的な治療のためには, 単に最先端設備の病院を作るだけではだめで, 新しい発想と深い洞察力を兼ね備えた名医あるいは医学者の登場を 待たねばならないのである.
地球赤道全体の実に1/8を占めるインドネシア列島は, 地質学的には実に新しく今から7000年ほど前に完成したと言われ, これによる適度な太平洋とインド洋との海水交換(インドネシア通過流)が 海洋大循環に果たす役割は, 現在WOCEその他の海洋観測・研究で最も重視されているところである. 実際, 現在のインドネシア列島は世界最高温の海水に囲まれ, これによりアフリカ・南米などという歴とした大陸に勝る 世界最活発な雲対流を育んでおり, そのため「海洋大陸」と称される. この世界最大の雲対流は, 周囲のアジア・オーストラリア両大陸と2大洋との間の複雑なモンスーン風系を 直接導いているのみならず, ENSOなど(エルニーニョとは要するに雲対流のインドネシアから中央太平洋へ の東遷に他ならない)の気候変動を含め, 地球規模大循環の第一義的な駆動源であると言って過言でない. この雲対流は成層圏への空気の取り込み口(ために「成層圏の泉」と呼ばれる) であり, その意味でオゾンホールその他の上層大気変動にも直接に影響を及ぼしている.
したがってインドネシア海洋大陸こそ, まさに現在の地球環境を規定している最も重要なツボなのである. まだアジア大陸と繋がっていた頃からここで直立猿人が暮らし, これが分離して海洋がちょうど世界を一巡した頃に, 各地古代文明は爆発的に発展した. 有史以後もこの領域は「海のシルクロード」として, 中国・日本など極東とインド以西の中東との両文明を結ぶ幹線の中継点となり, 東に発した明の鄭和の艦隊も, 遠く西から来たザビエルが乗る南蛮船も全てここを通過した. 航海上の要地であるから, 多くの気候・気象変動的な要素を含む伝承や風習がこの地には存在している. 例えば昔のジャワの暦は5日週と7日週を(ちょうど中国の十干十二支のように) 組み合わせて使うが, これから最近当地の雨季(ジャワでは11月〜2月頃であるが降雨は断続的である) の観測で見出されているものに近い 3日や18日の周期性が出る. またスマトラ島ミナンカバウ族の海の波を模した舞踊では, 女性達が並んで適当な時間差を置いて手をぐるぐる回すが, これは西欧の物理学者が前世紀になってようやく見つけた真実 (波に伴う海水各部分の運動は円運動である)に他ならない. これらは今のいわゆる自然科学者には無視され, 専ら民俗学者や歴史学者の研究対象となっているが, 数式にも言葉にもなっていなくとも明らかに物理学的発見であり, 今後例えば数百年スケールの気候変動などを論じる際には, 重要な根拠となるのではないかと考えている.
いわゆる科学的観測においても, この領域はインドより東の世界において最も早く行われたところである. オランダによるバタビア学術協会は1778年に創立され, 19世紀後半において既に1000を越す気象観測点が設けられていた. 大気中の潮汐波動に関する初期の研究は, 現在首都ジャカルタの気象庁本庁であるバタビア気象台のデータに基く. しかしながら例えばインドにおける英国とはかなり異なった植民地体制と, これに続く日本占領と独立戦争, 内部抗争などの不幸な歴史のため, 近年他の各地で導入されている最先端の大気・海洋観測は, なかなか当地には根付かずにいた. かくしてインドネシア海洋大陸は, 地球環境あるいは地球科学的にみて極めて重要であるにも拘らず, それらに関する国際的観測・研究の舞台になかなか登場できなかったのである.
京都大学超高層電波研究センターのグループでは, 地表近くから高度1000 kmまで一挙に観測することが可能な 超大型の「赤道レーダー」を中心設備とする, 「国際赤道大気研究センター」(ICEAR)を設立し, 海洋から超高層に至る様々の分野の研究者の協同研究体制を確立する構想を, 約10年前から温めてきた. その前駆段階が, 新プログラムの一環として津田教授を中心にジャワ島内で開始された 気球(1990年〜現在)・小型レーダー(1992年〜現在)観測であり, 実に様々の大気波動がこの観測から初めて見出されている. やはり新プログラムの一環として東大を中心としたグループにより, 海洋大陸域東端のパプアニューギニア近海において, WCRP-TOGAの大気海洋結合研究のための集中観測(1992〜3年)が行われた.
現在我が国の大気観測者の多くは, WCRP-GEWEXの関連でアジア大陸域に重点を置いて臨んでいるが, 筆者らは依然としてインドネシアでの観測を維持している. 津田教授らはさらにオーストラリアのグループと協同で, カリマンタン島に高度100 km付近を観測するレーダーを建設した. また並行して, 4000地点に及ぶ気象庁雨量観測などの既存資料のデータベース化や, 大気化学・生態学など広範囲の分野との共同研究 (例えばスマトラ・カリマンタン島内での広域森林燃焼の影響評価など), タイでのGEWEX-GAME観測との連携なども開始しつつある. これらは現在走っているGEWEX, WOCE, IGACなどの先に来る, 21世紀の気候変動研究計画(CLIVAR)などへ向けての重要な礎石の一つになると 確信している.
重要なことは, 以上のインドネシアでの観測活動は, レーダー設備等に要した予算は別として, 日本・インドネシア両国の研究者が完全に対等な立場で行っている, 少なくとも行おうとしているということである. 現在の観測作業は基本的に全てインドネシア側の研究者によって維持されており, またICEAR計画の提唱者である加藤名誉教授自身が バンドン工科大学客員教授となられたり, 様々な制度を使って多くの学生・院生・若手研究者を留学生・研究員として 京都大学に受け入れるなどのことを通じて, インドネシア人研究者自身によるデータ解析と研究成果発表を 強く推進している. 将来ICEARが実現した暁には, 周囲の他のアジア諸国そして欧米からの研究者をも広く迎え, まさに国境なき大気の観測・研究に相応しい国際協同研究体制となるはずである.
蛇足であるが, それでは上記のようなものが完成し, 地球環境の診察がほぼ完全に可能になったとして, 地球科学者は次はどこへ向かうのか? 答えの一つは両隣の火星・金星を始めとする他惑星環境であろう (既に米国は始めているではないかと言うなかれ, 人類は既に長いこと住んでいながらまだ地球環境を理解できずにいるのだから). 惑星科学的には, 現在の地球環境と惑星大気環境が如何なる道を通って 分化してきたかというのが一つの問題である. これは例えば現在の地球で温室効果がどんどん進めば, やがて金星のような灼熱地獄になるのか否かというような議論である. しかしそれらを互いに没交渉の患者と見るのでなく, 例えば冒頭に触れた火星起源の岩石のような惑星間の物質放出, 大気(地球では海洋も)の重力潮汐作用を通じた惑星間相互作用など, 各惑星環境の間の関連を考えるのも意味があるだろう.
もう一つの側面として, 環境バブル以後飛躍的に進展してきた各種地球観測の技術的拡張としての, (さらに言えば軍拡の時代の遺産の利用策としての) 惑星探査を見る向きもあろう. もっと現実的に, 例えば現在までの南極大陸がそうであるように, 各種資源やそういう利益の絡むものを含む政治的な動機が出て来ると 危ぶむ声もあるかも知れない. 住教授に言わせれば, 政治的・社会的なものが避けて通れないのが, 地球環境科学いや地球科学の運命である. 良かろう. そういうものへの対処にきちんとした指針を与え得るかどうかが, 今後の地球科学発展と地球環境解明への鍵と開き直り, 微力を尽くすことにしたい.