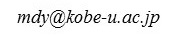山中大学ホームページ
山中大学ホームページ
我が地球の大気圏が人間活動により危機に瀕していると言われるが, 筆者はそれほど悲観的でも逆に楽観的でもない. 社会的な問題はさておき, 大気圏の基本的な成立ちや素過程の物理に余りにも謎が多いからである. 例えば地球温暖化の根拠となっている数値モデルでも, 対流圏の鉛直温度勾配をある臨界値(ふつう \( - 6.5 \mbox{K/km} \) )に調節したり, 雲の効果と称する鉛直流や加熱項を付加したりするが, これらは現在の大気の‘平均’的観測結果に基くもので, 成立条件等に必ずしも明確な物理的・定量的裏付けがあるわけではない. そのような大気圏内の素過程の曖昧さに立ち向かう努力の一端を紹介したい.
ところがこの「多重圏界面」の事実は, 不思議なことに研究者からは余り注目されなくなり 一旦ほとんど忘れ去られてしまう. 1940年代のレーダー追尾による風速測定の発明や高層気象観測網の全世界的拡大は, 前線上空のジェット気流の発見を導き, 温帯低気圧を偏西風の流体力学的不安定現象として解釈する契機を与えた. しかるにデータ解析は専ら温帯低気圧のスケール(水平波長数1000km)が 抽出できる程度に‘平均’化されたため, 対流圏界面については各半球1〜2箇所(顕著な前線の上空)にギャップがある という描像が定着した. 下部成層圏は放射による等温状態として冒頭に述べた臨界温度勾配を‘仮定’すれば, 対流圏の温度分布と圏界面高度は地上気温のみで決まるので, 太陽可視光による地上加熱の強い赤道域では極より高い圏界面が生じ, 地上気温ギャップのある前線上空では圏界面ギャップが生じると説明された.
一方, 1960年代から成層圏・中間圏の研究が本格化し, 安定に成層した惑星流体中を伝播する波動という新しい視点が確立されてきた. 1980年代までに, 下部成層圏や上部中間圏にそれぞれ鉛直波長1〜2kmおよび10km程度の 「重力波」(浮力復元力の流体波動)が存在し, この波が砕けて厚さ数100mおよび数kmの多重「乱流(小規模対流)層」を生成し, この砕け波によるストレスで中部成層圏(高度25km付近)や 中間圏界面(高度80km付近)は‘平均’的弱風状態であることが明らかになった. 東大の松野太郎教授と米国MITのリンツェン教授の1981〜82年の理論的研究を始め 内外の多くの研究者は中間圏界面に着目したが, 名大水圏研の田中浩教授と筆者は中部成層圏弱風層の生成を論じた. これについては, 筆者が1981〜86年に受託学生・ポスドクとして宇宙研に居させて頂き, 西村純・廣澤春任両教授の指導下に特殊風速計搭載気球による乱流層観測に成功し, また重力波による気球航跡の微妙な変化を肌で感じたことが大きい.
同じ頃, 京大超高層の加藤進教授らはMUレーダーを建設し(1984年完成), 全国共同利用・国際協同観測を開始した. コンピュータ制御による高速走査機能は 高い鉛直・時間分解能(150m, 1分)の3次元風速データの蓄積を可能にし, 津田敏隆氏らによる成層圏・中間圏「重力波」の気候学が構築されつつある. 筆者は1989年にこのグループに加わり, MUレーダー風速変動観測による下部成層圏「重力波」の構造と, 高層気象観測資料にある気温低極面の分布が極めて良く対応することに気付いた. 実はそれ以前に深尾昌一郎教授らが, レーダーエコー強度(乱流強度)分布から圏界面が推定できることを発見していた. 下部成層圏「重力波」はビヤークネスの発見した「多重圏界面」であったのである.
結局, 冒頭に述べた経験的鉛直温度勾配は「ミニ対流圏」の出現確率で決まっており, 対流圏とか成層圏とか言う‘平均’的温度構造による領域区分は この出現確率の違いによる区分と解すべきである. ある高度領域における「ミニ対流圏」の出現確率は, MUレーダーのような高分解能観測を長期間連続して行うか, または一定高度を長時間浮遊する気球の航跡を 大規模運動から予測されるものと比較しても推定できる. 極地研と宇宙研の協力でこの年末年始に 南極大陸周縁の成層圏高度1周に成功した大気球の航跡を, 気象官署の客観解析に基く空気の軌跡と比較することが期待される.
対流圏界面が1枚の面でなく時間・空間的に‘ゆらぎ’を伴うことで, 乱流による大気混合(鉛直輸送)およびストレス発生による偏西風抑制が起こる. 皮肉にも断片的なスナップショットでは見え, 多くのデータを‘平均’すると消えるノイズのようなものが重要なのである. 偏西風は極域を中心とする低気圧の周りの流れであり, これにストレスが働けば中心つまり極向きの流れが生じるが, これは放射過不足による鉛直流と連続していなければならない. 実際, 観測される「重力波」の波長や振幅の値はある程度揃っており, 従って極向きの流れや乱流混合も放射収支と同程度には一定のようである.
現在推進中のSTEP(太陽地球系エネルギー国際協同研究計画)の重要課題である 地球大気圏上下結合, つまり大気の‘相’平衡を根本的に解明するためには, 地球および他惑星の大気圏を詳細に観測し比較することが, 経験的プロセスを一切排除した数値モデルがない限りおそらく唯一の手段である. 一般に惑星が大気圏をもつための条件は 脱出速度より分子運動の遅い低温領域が生じることであり (脱出速度の小さい水星や月には大気圏がない), これが熱圏という‘相’のもう一方の境界を与える. また対流圏と接するもう一方の‘相’として 地球の大気成分(水)凝結による水圏(海)は考慮すべきであるが, 木星など巨大惑星本体の流体や, 地球でのオゾン光化学過程による中間圏の成層圏からの分離および 人類を含む生物圏の存在は, 当面の議論からは除外できよう. 結局, 惑星大気の‘相’として水圏・対流圏・成層圏・熱圏の4つを考えることになる.
今のところ具体的に研究対象となる惑星は地球・金星・火星の3つに過ぎないが, 金星の濃密大気(90気圧)の底には灼熱地獄(470$^{\circ}$C), 火星では希薄大気(数mb)の下に酷寒の世界(--90$^{\circ}$C)という極端な違いがある (図参照). 金星で温室効果を暴走させ厚い対流圏の‘相’として存在する炭酸ガスは, 火星では大部分ドライアイスとなった残りが成層圏の‘相’として存在し, 地球では水圏に溶存している. 残念ながらここから先の議論に必要な 金星や火星での「ミニ対流圏」の出現状態は全く未知に等しく, 特に金星対流圏下部は理論的にも技術的にも極めて困難とされてきた領域であり, 宇宙研で現在計画されている観測機投入に大きな期待がかかっている.
金星大気運動の問題のみならず赤道域は, 一般にどの惑星でも, また熱(太陽エネルギー入射量の再分配)においても励起源であり, かつ自転軸が水平となるため力学的に極めて特殊な状況となる. 実際, 1665年に初代パリ天文台長カッシニの発見以来謎のままの木星大赤班や, ごく最近(1989年)ボイジャー2号が見つけた海王星大暗班なども赤道域にある. 天才ビヤークネスは米国UCLAを67才で退官した翌年(1966年), 現在「エルニーニョ南方振動」と総称される地球規模気候変動の原因が 赤道域の海洋と大気との相互作用にあることを見抜き, 77才で没するまでこの問題の研究を続けたが, 実は地球ですら赤道域には未知が多過ぎて今なお完全には解かれていない.
地球の赤道域大気圏の解明を阻んできた, 広大な海洋との熱・水収支の複雑さや陸上の開発途上地域の多さは, 国際的かつ学際的な協力で初めて克服できる. そこでSTEPや海洋学や生態学関係の国際計画をも糾合した 文部省「新プログラム」(1990〜94年度)が, 地球で最高温の海水と最低温の成層圏が存在する インドネシア〜赤道西太平洋域を対象として, 大気科学分野では加藤教授らの力学観測, 田中正之東北大教授らの組成・化学観測, 松野教授らのモデリング・データ解析の3課題で始まった. このうち力学観測は東大の住明正氏らの大気海洋相互作用と 深尾教授らの対流・波動発生機構の2項目から成り, 後者を筆者も分担している.
観測は常にチームワークを必要とするが, 上記の赤道大気観測は国内や欧米諸国の研究者のみならず, インドネシアを始め東アジア諸国の各方面の人々との密接な協力, しかも大気現象のスケールを考えれば将来への永続的発展が必須である. そこでインドネシア超大型レーダーを中核とした 国際赤道大気研究センター(ICEAR)の建設が, 国際学術組織の積極的支持のもと加藤・深尾両教授を中心に計画されており, 完成の暁には筆者も現地永住の計画を立てている. まだ道は決して近くないが, インドネシアの若者とともに地球の, そして金星や木星の赤道大気の謎を解明する日が必ず来ると信じている.
図1 地球(○)・金星(♀)・火星(♂)・木星( )における大気圏鉛直構造 (気圧に対する気温の分布)の‘スナップショット’の模式図. 矢印は‘平均’的な対流圏界面を示す.